
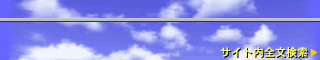
 |
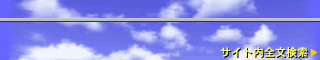 |
||||||||||||
 |
生活・漂う風景 / 04.05.10公開 07.07補遺 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新 生活・漂う風景 住宅街にそびえる壁の存在〜武蔵野貨物線大宮支線〜Existence of the wall in a residential section
身近に広がる風景を一歩立ち止まって眺めてみると、そこにはさまざまな謎や不思議があります。 壁の正体を見る〜現地探訪記〜
さて今回は、大宮支線を線路の外から見てみようということで、現地へ赴いてみることにしました。4月中旬、花曇りながらも暑い日でした。 地形図や道路地図を見ると、与野〜北浦和間で地下トンネルにもぐり、埼京線中浦和付近で地上に出ることが分かりますが、トンネルの途中でトンネル部分を示す破線が消え、何かが覆い被さっているような部分があります。上の地図でピンク色に塗られた部分です。 この部分は一体何があるのだろうかと興味を覚えてきます。場所は中央区大戸1丁目。さっそく現地調査です。 浦和駅から国際興業バス浦13、浦桜13系統「大久保浄水場」行に乗り約7分、「水道局営業所」停留所で下車します。この停留所は以前「水道記念館」という名称でしたが、2003年3月31日付けで水道記念館が閉館したことから、隣接する施設を新たな停留所名にすることになりました。 水道局の脇を歩くこと2分。正体が見えてきました。
写真1は常盤6丁目15番付近の駐車場付近にある境界標です。ちなみにこの駐車場はJR東日本の用地で、JR東日本の関連会社が駐車場を管理しています。 それでは、もう少し歩き進めてみることにします。
写真5は常盤6丁目20番付近。目の前で見た印象はまさに壁。この壁の中を列車が走っていることを思うと不思議な気分です。この場所を列車が通過するときに通過音が聞こえるかどうかは分かりませんでした。ちなみに高さは2階建て住宅より少し低めです。
写真8は大戸1丁目13番付近。ここで市道と交差し、コンクリートの壁はここで消えます。こっそりコンクリート部分を歩いてみましたが、特に変わった感覚はありません。写真10(写真9は欠番)を見るとよく分かりますが、コンクリート部分は平らに貫かれていて、脇の市道が与野方面より登り勾配になって大宮支線と交差しています。
消えたコンクリートの先には造成中の分譲住宅が見えます(写真11・画像はモザイク処理)。この住宅のすぐ下に武蔵野線の貨物列車が走っているということを、未来の住人はいつ知ることになるのでしょうか。
大戸1丁目8番付近にさしかかると、もうトンネルの姿は見えず、民家や道路の下を貫いています。次に姿を見せるのは1丁目9番付近です。写真13はトンネル口の真上にある信号関係の機器ボックス。
トンネル口付近は、近隣の別所沼や鴻沼川の支流に挟まれており、現在も緑が多く残っている地域です。先ほどまでの無機質なコンクリートを見たあとで、水鳥の姿を目にすると閉塞感から解放されます(写真15、18)。 トンネルを抜けると大宮支線のガード下を歩いていきます。写真16の案内板には「大宮支線」の名が見えます。写真17はこのガードの銘板(空頭標)。写真では分かりづらいですが、「協定年月日 昭和43年11月21日」と記載されています。
まもなく中浦和駅に近づいてきました。 今回の現地探訪もここで終わりです。写真21は関1丁目8番付近から与野方面に延びる大宮支線の線路です。左側が西浦和からの支線、中央が武蔵浦和から大宮方面の支線、そして右が武蔵浦和から南浦和、越谷方面の支線(西浦和支線)です。地図で見るとデルタ線の頂点部分に位置します。 帰路は近隣の「関」停留所より志01系統などの路線バスで浦和駅に戻ります。 地形が生み出したコンクリートのシェルター 武蔵野線は1960年代に、都心の旅客輸送量の増加、加えて貨物輸送の確保のため、山手貨物線に代わるルートとして京葉線とともに貨物輸送専用の路線として建設されました。路線は首都圏をぐるっと囲み、東海道、中央、東北、常磐、総武の各線と連絡し、旅客輸送で混雑する都心を通らずに貨物を輸送できるようにしたほか、効率よく荷さばきできるよう沿線には巨大な貨物基地(ターミナル)が建設されました。 路線はすべて踏切がなく、各線と接続する部分も高速道路のインターチェンジのように立体交差となっています。また、騒音や用地買収などの理由から、トンネル部分が多いこと、さらに貨物輸送を目的とするため、勾配やカーブが緩く作られていることも特徴です。 今回訪れた大宮支線は、東北本線と連絡するルートとして作られたもので、先に述べた理由から支線のほとんどの区間はトンネルになっています。与野〜北浦和間で潜るトンネルは「浦和トンネル」と呼ばれ、反対側の西浦和方は「与野トンネル」と呼ばれており、それぞれ別の名前がついています。しかしこの区間を列車で走ると一本のトンネルが続いているように見えます。 執筆当初、「与野〜北浦和付近で潜るトンネル」を「与野トンネル」と記載しておりましたが、後日調査で逆であることが分かりました。トンネルのある行政区画に併せて命名されており、与野駅方の「浦和トンネル」は旧浦和市の北浦和、常盤付近を、西浦和方の「与野トンネル」は旧与野市の大戸付近を通っています。 この2つのトンネルを挟んでいるのが、今回取り上げたコンクリートの「壁」、すなわち「シェルター」です。
関連リンク
→資料:車内からの映像(Podcasting STIJサイト)
関連サイト
→埼玉県さいたま県土整備事務所
参考文献
鉄道ピクトリアル 2002.8(通巻720号) 特集 JR武蔵野線・京葉線 |
|